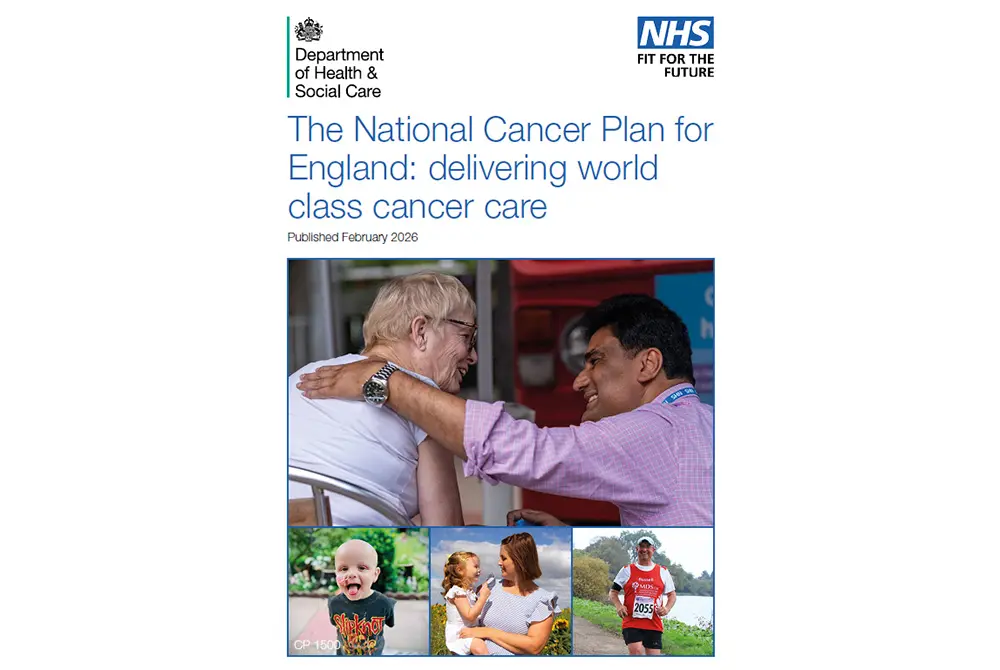胃がん検診で内視鏡検査はどのくらい有効か、帝京大学の濱島ちさと教授に聞く Vol.2
胃X線検査との役割の住み分けには課題も

2016年、胃がん検診に内視鏡が対策型検診として位置づけられた。早期の胃がんを検出する能力を持ち、胃がんによる死亡を防ぐ、内視鏡の有効性が評価された形だ。長く実施されてきたいわゆる「バリウム検査」の胃X線検査が広く行われているが、内視鏡検査の受け方をどう考えるとよいのか。引き続き帝京大学医療技術学部看護学科教授の濱島ちさと氏に、日韓比較研究の結果などを踏まえ、胃がん検診の課題やこれからを聞く。(聞き手/PREVONO編集長 星 良孝)
──約10年前に胃がん検診ガイドライン改定版を公表した。
濱島氏:胃がん検診も、状況は動いています。
2016年(2016年4月1日適用の改正)、厚労省の指針で、対策型胃がん検診の検査として胃内視鏡検査が追加され、胃X線または胃内視鏡の選択制となりました。そこから全国に広がっていきましたが、現状では導入はまだ十分ではなく、実施していない市町村が約4割です。
背景には、内視鏡を担える専門医が不足し、実施できる人材が限られるという供給側の制約があります。
──内視鏡が承認されたとしても広がるのは簡単ではない。
濱島氏:都市部を中心に徐々に浸透している一方、地方ではまだ広がり切っていません。そのため、内視鏡を軸にしつつ、実施できない地域ではX線が続いています。
──いわゆるバリウム検査、胃X線検査は1983年から制度として実施されており歴史が長い。
濱島氏:内視鏡が広がる中で胃X線検査がどのような役割を担っていくのかという点は課題として残されています。
2016年に内視鏡が承認された当時は、内視鏡を入れるかどうかというのが最大の焦点。胃X線検査はどのように位置付けるのか、検診を受ける人たちの年齢、検診の頻度など、より掘り下げた論点は十分に詰め切れなかった部分がありました。
元々、胃X線検査は40歳以上、毎年という形で行われていました。内視鏡が導入されるに当たり、内視鏡は50歳以上、2年に1回と位置付けられましたが、胃X線検査の対象年齢や頻度をどうするかという問題がありました。
当時は、胃X線検査の年齢や頻度は当面従来のままになりました。
──運用を大きく変えるには調整すべきことも多い。
濱島氏:会社員を対象に会社で行われる職域検診では、胃X線検査が40代が中心に行われています。そうした中で開始年齢を50歳に上げることの影響は大きいです。一方で、自治体からは「1年と2年が混在すると負担が増えるからそろえたい」といった要望も出てきます。
──どのように胃がん検診を行えば胃がん死亡率を減らせるのかを見極める必要がある。
濱島氏:私は2024年、オランダ、エラスムス大学の研究者と共同で、日韓それぞれの胃がん検診が本当に死亡率を下げているのかを確かめました。モデル解析のような新しい手法も用い論文として発表しました。検診の分野では国際的にも評価の高いGastroenterology誌に論文は採用され、専門家からも注目された結果です。
前提として、日本と韓国では胃がん検診の導入時期には差があり、日本は1983年から胃X線検査が行われていたのに対し、韓国は2000年前後に内視鏡主体で導入しました。日本は内視鏡導入が2016年で、それ以前は胃X線検査主体でした。導入時期と方法の違いを踏まえ、効果をどう評価しました。
──どのような結果に?
濱島氏:韓国は、胃がん検診を最初から内視鏡主体で導入し、受診率も高かった。そのため、導入直後から胃がん死亡率が下がっていました。
一方、日本は、導入時期こそ古く、20年以上前から胃がん検診が制度として存在してきました。そうした中で、胃がんの死亡率は当初は検診のおかげで低下したことが確認されました。その後も徐々に低下していたのですが、低下を「検診を実施したことによる上乗せ効果」としてみると、2000年頃以降はほとんど上乗せ効果がないという結果になりました。
つまり、見かけ上、胃がんの死亡は低下していたのですが、あくまで自然減と推測できたのです。
胃がんになる人々の背景にある要因によって減少しているだけである可能性が高いと考えられました。というのも、胃がんの原因として、ピロリ菌の関与が知られています。1980年前後は、まだ40代で胃がんになり亡くなる方はいました。その状況は変化し、最近では胃がんで亡くなる方は60代、70代になっています。そうした状況の変化により胃がん死亡率は減っています。
──胃がんが減っているからといって、検診の成果だと言えない可能性がある。
濱島氏:ピロリ菌感染率が下がってきていることは、韓国でも日本でも共通しています。だから胃がん罹患率そのものが減る方向にはあるわけです。
しかし、検診をやった分の上乗せ効果があるかという視点で見ると、韓国では効果が見えるのに対し、日本ではほとんど見えない。胃X線検査が担っていた役割は、時代とともに相対的に小さくなっている可能性があります。

──なぜ日本のX線検診は上乗せ効果が見えにくい?
濱島氏:理由の一つは、胃X線検査の精度の問題が考えられます。
胃X線検診が1960年代に始まり、地方に検診車が回るようになりました。その当時は、診断も診療も現在とは比べものにならない状況で、胃がんを見つけるインパクトは大きかった。
ただ、1980年代に制度として胃X線が導入された後、日本は胃X線主体が続き、内視鏡は広く普及せず、基本的には内視鏡は専門医が行う検査の位置づけでした。
胃X線検査は、ごく早期の胃がんを見つけ出すことは難しいです。内視鏡の普及がなかなか進まない状況で、胃がん死亡の低下にはつながりづらかった可能性があります。
──今は状況が変わってきた。
濱島氏:現在では内視鏡そのものの性能が一層向上しました。その上に、医師の研修制度の変化もあり、研修の段階で手技を学べる環境が広がり、実施できる医師が増えました。
診療の現場では、以前は限られた施設でしかできなかったことが、一般的な検査として多くの病院で普通に行えるようになってきました。さらに、内視鏡で病変を確認したら、そのまま切除する治療技術も2000年以降に確立、進化し、今では多くの病院で実施可能になっています。こうした背景の中で、胃X線検査が担っていた役割は相対的に小さくなってきました。
──受ける側の行動も変わっている。
濱島氏:一般の受診者のイメージとしても「内視鏡の方が精度が高い」「できるなら内視鏡を受けたい」と考える人が増え、診療でも内視鏡が身近になった結果、胃X線検査による検診の受診率はどんどん目減りしました。
今では地域によっては、住民検診の受診率が一桁台に近いところまで落ち込んでいます。こうなると、胃X線検査による検診を続けても「上乗せ効果」がほとんど期待できません。
──前回の胃がん検診ガイドラインを改定した時点から情報も増えている。
濱島氏:前回の胃がん検診ガイドラインを作成した時点では、そこまで明確な証拠が揃っていませんでした。導入後に追加の検討を重ねる中で見えてきた点も多くあります。だからこそ胃がん検診は重要な岐路に立っていると感じています。
──胃がんを減らすために最適な検診とは。
濱島氏:胃がんは減っているとはいえ、世界的に見れば日本の胃がん罹患、死亡が低い水準というわけではありません。特に男性の60代以降では依然として重要です。70代をどこまで対象にするかは議論が必要ですが、少なくとも60代はまだ検診が必要な層です。
60代は、職域で検診を受けていた人が定年退職し、自身の意思で検診を継続している人がいるものの、多くが国保に移行する時期となります。つまり検診機会を失いやすい谷間の時期です。この層にきちんと受けてもらう設計が重要になります。
──内視鏡を受けやすくするための環境作りも考える必要がある。
濱島氏:限られた内視鏡を行う人材、設備などの資源を考えるとき、相対的にリスクの低い若年層、例えば40代で慣習的に受けているところは抑えて、その分をむしろ検診が必要な60代に振り向ける、という発想も必要になるでしょう。
ただ、年齢で区切る議論は、どうしても抵抗が強くなります。医療機関の検診からの収益にも関連しますから、関係団体の中でも難しいテーマになりやすいのです。
──胃がん検診の運用を変えるのは簡単ではない。
濱島氏:今、2種類の検査方法が並立して走っている状態です。だからこそ、胃X線検査をどう位置づけるか考え直す時期に来ていると考えています。(続く)
プロフィール

濱島ちさと(はましま・ちさと)氏
帝京大学医療技術学部看護学科教授(保健医療政策分野)。帝京大学大学院医療データサイエンスプログラム兼任教授。医学博士(岩手医科大学、公衆衛生学)。専門分野は、がん検診、医療技術評価(HTA)、臨床疫学、公衆衛生学。1983年に岩手医科大学医学部を卒業後、同大学大学院で公衆衛生学を専攻し博士課程を修了。癌研究会附属病院検診センター医員を経て、慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室助手、聖マリアンナ医科大学予防医学教室専任講師などを歴任。2003年より国立がんセンター(のち国立がん研究センター)で検診評価・がん情報分野の要職を担い、がん予防・検診研究センター/社会と健康研究センターにおいて検診評価研究室長などを務めた。2018年から現職。国立がん研究センターのがん検診ガイドライン作成に2003年から関わり、2018年からは文献レビュー委員会委員長としてガイドライン作成の基盤整備にも携わる。IARC(国際がん研究機関)のハンドブック作成(乳がん・大腸がん・子宮頸がん領域)等に参画。学会活動では、日本消化器がん検診学会理事などを務め、第59回日本消化器がん検診学会大会(JDDW2021)では大会長を務めた。日本学術会議連携会員。
参考文献
Lopes G, Stern MC, Temin S, Sharara AI, Cervantes A, Costas-Chavarri A, Engineer R, Hamashima C, Ho GF, Huitzil FD, Moghani MM, Nandakumar G, Shah MA, Teh C, Manjarrez SEV, Verjee A, Yantiss R, Correa MC. Early Detection for Colorectal Cancer: ASCO Resource-Stratified Guideline. J Glob Oncol. 2019 Feb;5:1-22. doi: 10.1200/JGO.18.00213. Erratum in: JCO Oncol Pract. 2022 Nov;18(11):775-778. doi: 10.1200/OP.22.00580. PMID: 30802159; PMCID: PMC6426543.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30802159/

この記事の執筆者
星良孝
PRENOVO編集長。東京大学農学部獣医学課程卒。日経BPにて「日経メディカル」「日経バイオテク」「日経ビジネス」の編集・記者を担当後、エムスリーなどを経て2017年にステラ・メディックスを設立。ヘルスケア分野を中心に取材・発信を続ける。獣医師。